■ DAY 7
“それ”は最果ての海で生まれる。
夏のはじまりに海より訪れ、夏の終わりに海へと還った。

“彼女たち”は人と共には暮らせない。
ひとたび海から離れようものなら、砂粒のように細かな泡となって息絶える。

人は一時期、呪われた彼女たちを“人魚”と呼んだ。
流刑が始まるより昔、街ではよく子どもが消えた。

年々、街へと戻ってくる人魚の数は変動した。
消えた子どもと同じ数だけ、きっかりと。

やがて流刑が始まる。
人魚に“巫女”の名と小舟と生贄を与え、最果ての海に送り出すことになった。
その翌年、生贄とされた罪人と同じ数の人魚が戻ってきた。

海より現れる彼女たちの正体を誰も知らない。
彼女たちもまた、世界が終わる場所で生まれたこと以外を語らない。
彼女たちは今年もまたひと夏を終え、
何かに呼ばれるかのように在るかも分からない世界の果てへと消えていく。
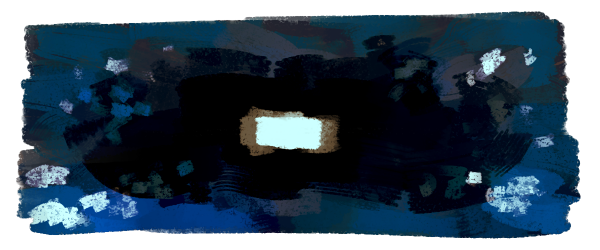
輪廻を外れ、孤独ないのちを繰り返す者たち。
無垢なる邪悪は海へと還り、産まれ、永遠を巡り廻り続ける。
すべてを洗い流し、ましろになって、魂の贖罪が終わるその日まで。

この島に流れ着いた日よりもずっと、潮が高く満ちていく。
木にくくったままのおんぼろのいかだは日に日に少しずつ浮いていった。

旅の再開は近い。