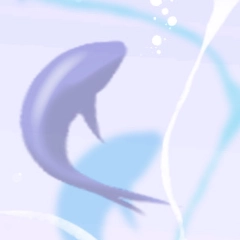RECORD
【日記20】梅雨入りの話
蛇の目でお迎えに来てくれたのは、母親ではなく。
「居たのショウ兄やったんよな」
「来てくれたのは、ねね婆だった」
「嬉しかったなあ、あれ」
「……嬉しかったよ」
「ええ。向こうはもう水無月を迎えて少し。
先日はお誕生日でございましたでしょう?
であるのならば。」
「開けるなら今日が丁度よろしいかと存じます。
あちらの気候に合わせてみてもよいのでは?」
「……毎年忘れちまっていけないな。
暦ってのはどうにもこう身につかないもんだ。
そうだな、丁度いい。今日開けるか」
「おう、今日開けるのか?
常の細石の方の河童御前もそろそろかね。
みかまりのみちは……あちらさんは気まぐれだが」
「そういや景気よく土砂降りにしてトラブルになったな。
あの時はちょっと羽目を外しすぎた。気を付けよう」
「ではこちらへ。若旦那様、足元お気をつけて」
「ああ。結構狭いんだよなここ……よっ、と」
それがあるのは累卵道のとある一角。家と家のわずかな隙間に挟まれている、よく探さなければ見つからない小さな扉の向こう。
おもむろに置かれている盥一杯の濁った水を根城にするのは、ゆらりと泳ぐ鮒一匹。
「東の都は梅雨入りだ。派手に往きましょうや」
雨乞い。神仏に祈願し慈雨を求む。
それは世界各地で見られる宗教的な儀礼だ。無論それは表も裏も例外なく、ここでも同じように祈り開ければ。然ればたちまちこの通り。
───開けよ開け開け、水神御納戸!
盥からぶわりと雲が膨れ上がった。
本来暑い時期に自然発生する積乱雲に似たそれが、もくもくと形を成して、しかし育ちきることはなくある程度の大きさで留まる。螺千城全体を覆うことはなく、たった一区画だけ、ささやかな狭い範囲をしとどに濡らす慎ましい雲。
それを青年はまるで綿飴でも作るように、傘の石突でくるりと絡めとって引き上げる。
累卵道にほんの一時だけ雨が降り出した。
雨がトタンを、木材を、瓦を、茅葺を。
ひしめき合う材質様々な屋根を濡らしていく。
住民達が何人か家から飛び出して来た。
大きな水瓶を引っ張って来て軒先に並べだす。器の形状をしていれば十分だと釜や鍋、果ては湯呑に茶碗までもが皆一様にして整列している。
「あれ?もうバケツってないんだっけ?」
「アンタが持ってるそれで最後だよ。
ほら早く貯めないと雲が逃げちまう!急げ急げ!」
「あらまあ……ご自宅の水道から
錆水が出る方達は大変ですのねえ……」
「ケッ、良い御身分なこった。
こうしちゃいられねえ、俺らも水を汲まないと。
最近は水売りも高ェからな」
「マタネ、若旦那!ミケチャン!」
「この時期に1回だけ、梅雨入りを転機に
開けさせて貰ってるが……次はいつになるだろう。
もう少し暑くなってからか」
「えっ、あ、わ、分かった。すぐ行く」
ウチも水道から錆水しか出ねえんだよ!
大慌てで水神御納戸を後ろ手に閉める。やがてカラリと晴れて、いつものように夕陽が差し込んでくるまで。累卵道には薄く水が張って家々を反射していた。
そうして家の中の皿と言う皿を、器と言う器を外に出した後。
ぴたぴたと跳ねる水滴の音に、青年はふと思い出したように顔を上げた。
「ミケ、少し空ける」
「お出かけでございますか。いってらっしゃいませ」
浅葱色の傘をさして累卵道を往けば、近所の子供たちが傘をささずに降りしきる雨にはしゃいでいた。
昔は自分も同じように傘をほっぽりだして遊び、濡れ鼠で帰って来ては、世話になっている人に叱られていたのを思い出す。
思わず口元に笑みがこぼれた。
朝焼け夕焼けばかりのこの世界で、真水の入手手段が限られている螺千城で、雨は非日常の一つとして輝きを放っている。
路地に張った水が鏡のように反射して、ただでさえ縦に長い螺千城をさらに縦へ引き延ばす。
足元に映りこむ橙色。聳え立つ家の隙間に広がる空の景色が、今は青年の足元にある。
そんな風にいつもは見上げる空を、今だけは足の間から覗き込むのが存外面白い。
天地無用もなんのその。雨が降った時ならば、この世界はいとも簡単にひっくり返るのだ。
雨がまばらになった頃、青年の周りにいくつかふよふよと赤い尾ひれの金魚が戯れだした。
羽織の隙間にもぐりこんだり、首筋をくすぐったり、柔く肌を滑らせてくる。
「エサクレ!」
「エサホシイ!」
「ワカダンナ!」
「エサナイノ?」
「エサー!」
「ユビ!」
「ウデ!」
「アシ!」
「指も腕も足も駄目だ。やらないよ」
「ケチ!」
「ケチンボ!」
「吝嗇で結構」
口々に好き勝手言う金魚達に好きにさせていると、やがて一回り大きな金魚と相見える。
風に舞うカーテンのように鰭を動かして、その金魚は優雅に揺蕩っていた。

「これお前たち、たかるのはおよし。人間を食ったら腹を壊しちまうよ」
「紅御殿。ご機嫌麗しゅう」
「雨を引き連れてよく来たねえ若旦那。随分と久しぶりに会った気がするけれど」
「雨の降る日にしかアンタに会えないからな」
「普段のここはどうにも乾涸びていてよくないよ。毎日雨が降りゃいいのに」
「それじゃ累卵道が水浸しになっちまうだろ」
紅御殿と呼ばれた金魚は鰓からごぼりと泡を吐いた。
笑ったような、怒ったような、判別の出来ない声で仰々しく言う。
「こんな街、いつか沈んじまえばいいのさ。綺麗な水が足りないんだろう?一生溺れて暮らせるよ」
「大した野望だ。言いだしてかれこれ何年だ?」
「ハハ! 言うようになったじゃないか、小童」
紅御殿はその身体をゆらゆらと揺らして、楽しげに泡を吐く。
本気ではない、ただの軽口の応酬だ。その証拠に次に出した声はやわらかく優しいものだった。
「また次の雨に会おう、若旦那。達者で暮らしな」
「ああ、紅御殿も息災で」
「ねね婆によろしく言っておいてくれるかい」
「なんて言えば?」
「決まってるだろう。【一体いつになったらくたばるんだい】だよ!」
青年は珍しく声を上げて笑った。